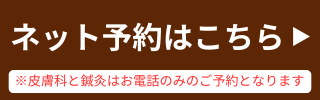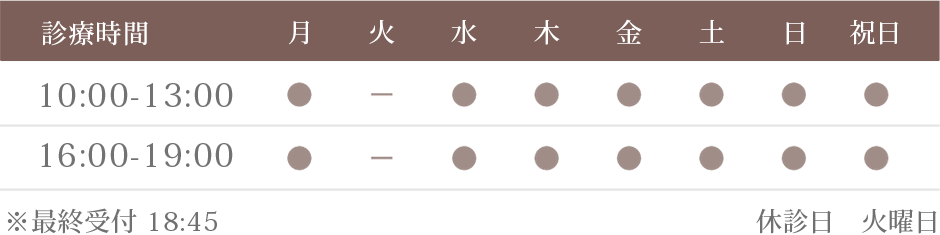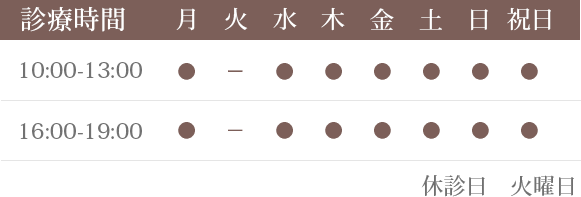BLOG
犬の皮膚病が治らない|それって内分泌疾患が原因かも?

広尾・恵比寿・西麻布・南麻布を中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」です。
犬の皮膚に異変が現れると、脱毛や痒みなどの症状に不安を感じ、動物病院を訪れる飼い主様も多いです。皮膚病の原因としては、アトピー性皮膚炎やマラセチア症などがよく挙げられますが、中には内分泌疾患(ホルモンの病気)や代謝疾患が隠れているケースもあります。
これらの疾患は、適切な診断と治療が必要ですが、早期発見と治療によって症状を改善させ、愛犬の生活の質(QOL)を向上させることが可能です。
今回は内分泌疾患や代謝疾患について、代表的な病気である「クッシング症候群」の診断方法や治療方法、そして生活管理のポイントなどをご紹介します。
■目次
1.内分泌疾患とは?
2.代謝疾患とは?
3.クッシング症候群の診断方法・治療方法
4.生活管理とケア方法
5.よくある質問(Q&A
6.まとめ
内分泌疾患とは?
内分泌疾患とは、ホルモンの分泌異常によって体内のバランスが崩れる病気を指します。ホルモンは体内で重要な調整役を担い、糖やミネラルの代謝、エネルギー消費、免疫機能の調整などを行います。しかし、ホルモンの分泌が多すぎたり少なすぎたりすると、全身にさまざまな症状が現れることがあります。犬でよく見られる代表的な内分泌疾患は、以下が挙げられます。
<クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)>
副腎から分泌されるホルモン「コルチゾール」が過剰に分泌される病気です。コルチゾールは、炎症を抑える働きやエネルギー代謝を助ける役割を持っていますが、過剰になると以下のような症状を引き起こします。
・多飲多尿(たくさん水を飲み、尿が増える)
・左右対称性の脱毛
・多食(過剰に食べたがる)
・腹囲膨満(お腹がぽっこり膨れる)
特に中高齢の犬に多く見られ、トイプードルやダックスフントなどの犬種で発症しやすい傾向があります。
<低血糖症>
血糖値が異常に低くなる状態で、生後間もない小型犬によく見られます。糖の生成や蓄積がうまくいかないため、ふらつきや嘔吐、意識障害を引き起こすことがあります。また、副腎皮質機能低下症や糖尿病治療の過程で過剰にインスリンが投与された場合にも発症することがあります。
代謝疾患とは?
代謝疾患は、体内で栄養素をエネルギーに変換する機能に異常が生じる病気です。代表的な代謝疾患は、以下が挙げられます。
<糖尿病>
膵臓から分泌されるインスリンの機能が低下し、血糖値が異常に高くなる病気です。糖尿病の症状としては、多飲多尿、多食、体重減少などが挙げられます。遺伝や加齢が発症リスクを高める要因とされ、犬では治療にインスリン補充が必要となる場合がほとんどです。
<リポ蛋白代謝異常症>
リポ蛋白(脂質と結合したタンパク質)の代謝に異常が生じることで、高脂血症を引き起こす病気です。この疾患は、特定の犬種で発症リスクが高いとされ、遺伝的な要因が強く関与しています。
<ビタミン・ミネラル代謝異常>
ビタミンやミネラルの代謝に異常がある場合、それぞれの不足や過剰により皮膚症状や内臓疾患が現れることがあります。例えば、ビタミンA不足は皮膚の乾燥や脱毛を引き起こすことがあります。
クッシング症候群の診断方法・治療方法
<診断方法>
クッシング症候群の診断では、まず視診や触診で外見上の異常を確認します。その後、超音波検査で副腎の大きさを調べたり、ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)刺激試験という特殊な検査を行ったりします。これらの検査により、副腎からのホルモン分泌量や機能異常を確認します。
<治療方法>
クッシング症候群の治療では、一般的にコルチゾールの過剰分泌を抑える薬を投与します。適切な投薬治療により、症状が改善されるケースが多いですが、病気の進行具合や犬の体調によっては治療法を慎重に選ぶ必要があります。副腎腫瘍が原因の場合には、外科手術が選択されることもあります。
生活管理とケア方法
内分泌疾患や代謝疾患の予防と管理には、以下のような日常生活でのケアが非常に重要です。
<食事管理>
犬の健康状態に応じた適切なフードを選ぶことが大切です。内分泌疾患や代謝疾患を持つ犬には、療法食を取り入れることで症状の改善が期待できます。また、脂肪分の多いおやつや人間の食べ物は控えましょう。
<適切な運動>
適度な運動はストレス解消や代謝機能の向上に役立ちます。犬種や年齢に合わせた運動を心がけ、無理のない範囲で毎日続けることが大切です。
<ストレス管理>
犬にとって過剰なストレスは、皮膚症状やホルモンバランスの乱れを引き起こす原因となることがあります。愛犬がリラックスできる環境を整え、適度なスキンシップや遊びを通じてストレスを軽減しましょう。
<季節ごとの注意点>
夏場は暑さによる脱水や熱中症のリスクが高まるため、涼しい環境を提供し、水分補給をこまめに行いましょう。一方で、冬場は寒さがストレスや代謝低下の原因となるため、暖かい寝床を用意し、室内の温度を一定に保つことが重要です。
よくある質問(Q&A)
Q:甲状腺の病気と診断されたが、いつまで経っても治りません。
A:ホルモンの病気は完治が難しく、生涯にわたる管理が必要なことが多いです。甲状腺の病気による脱毛も、治療開始から改善までに時間がかかるケースがあります。当院では、「単なる脱毛症」と思われた犬が、実際には内分泌疾患だったという事例もあります。諦めずに治療を継続しましょう。
Q:内分泌疾患の犬に留守番をさせても大丈夫ですか?
A:短時間の留守番であれば問題ないことがほとんどですが、毎日の投薬を守ることが前提です。不安がある場合は、ペット用モニターカメラを利用するのもおすすめです。
Q:最近、性格が変わった気がするのですが、ホルモンの影響ですか?
A:ホルモンの乱れが性格の変化を引き起こすことがありますが、高齢犬では認知機能低下など他の原因も考えられます。動物病院で適切な診断を受けることをおすすめします。
まとめ
犬の皮膚病がなかなか治らない場合、その背後に内分泌疾患や代謝疾患が隠れている可能性があります。これらの疾患は見た目だけでは判断できないため、早期に検査を受け、適切な治療を行うことが重要です。
日常的な観察や生活管理、そして定期的な健康診断を通じて、愛犬の健康を守りましょう。不安があれば、早めに動物病院に相談し、専門的なアドバイスを受けてください。適切なケアを通じて、愛犬が健康で快適な生活を送れるようにサポートしていきましょう。
広尾・恵比寿・西麻布・南麻布中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」では定期健診に力を入れており、病気の予防と長期健康維持のお手伝いをしております。
■関連する記事はこちらから
犬の甲状腺機能低下症┃加齢のせいと判断せず早めの受診を
「広尾・恵比寿・西麻布・南麻布」を中心に診療を行う
広尾テラス動物病院
当院のWEB相談・お問い合わせフォームはこちらから